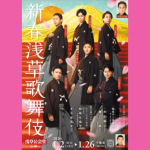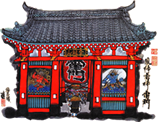二尊仏-奉納金銅座像仏(にそんぶつ)
「濡れ仏」の名で知られる二尊仏は、貞享4年8月に、江戸時代初期に神田鍋町の太田久衛門正儀によって作られた。この二尊仏は、観音、勢至の二著薩から成り、像の高さは共に2.36mで、蓮台を含むと4.5mにも及ぶ。願主は、上野国(現、群馬県)の高瀬善兵衛という人で、かつて奉公した日本橋伊勢町の米問屋への謝恩と菩提のために建立した。観音像は、旧主善三郎の菩提を弔うため、勢至像はその子次郎助の繁栄を祈るためと、蓮弁台座銘に記されている。基壇の組石は、長さ約12m、幅6.21m、高さ1.5mとなっている。
地蔵菩薩像(石造)
延宝5年(1677)松村一洞軒宗智居士。
地蔵菩薩像
廊誉見我大和尚ほか菩薩のため、日本橋石町の寺田長左衛門ほか5名で造立。
阿弥陀如来像(石造)
浮誉法霊信女ほか菩薩のため。相模屋五兵衛ほか15名で、寛文11年(1671)造立。
阿弥陀如来像(石造)
数十人の霊名が刻まれている。承応3年(1654)造立。
平和地蔵像(石造)
太平洋戦争の殉難死者菩薩のため、昭和24年に龍郷定雄氏の造献。
母子地蔵
第二次世界大戦中満州でソ連の参戦に逢い命を落とした母親と子供の冥福を祈るため平成9年4月「まんしゅう地蔵建立委員会」の建立。尊像発案者は漫画家のちばてつや氏。
久米平内堂-文付け、恋の仲立ち(くめのへいないどう)
久米平内(くめのへいない)は天和3年(1683)に没したと言われる人の名で、剣の道に優れた平内は多くの人を殺したので、自分の罪を償うために晩年浅草寺内の金剛院に住み、自らが禅に打ち込む「仁王座禅」の姿を石に刻ませ、自分が死んだら人通りの多い仁王門の近くに像を埋めて”踏み付け”させたという。それが転じて「文付け」となり、恋の仲立ち役の神様となって崇拝され今に伝わっております。現在でも「縁結び奉納箱」が設置されていて、恋の願いを入れる事が出来るようになっていて久米平内のご縁日である毎月6日には投函された願いを浅草寺で願い成就のお焚きあげを行っております。